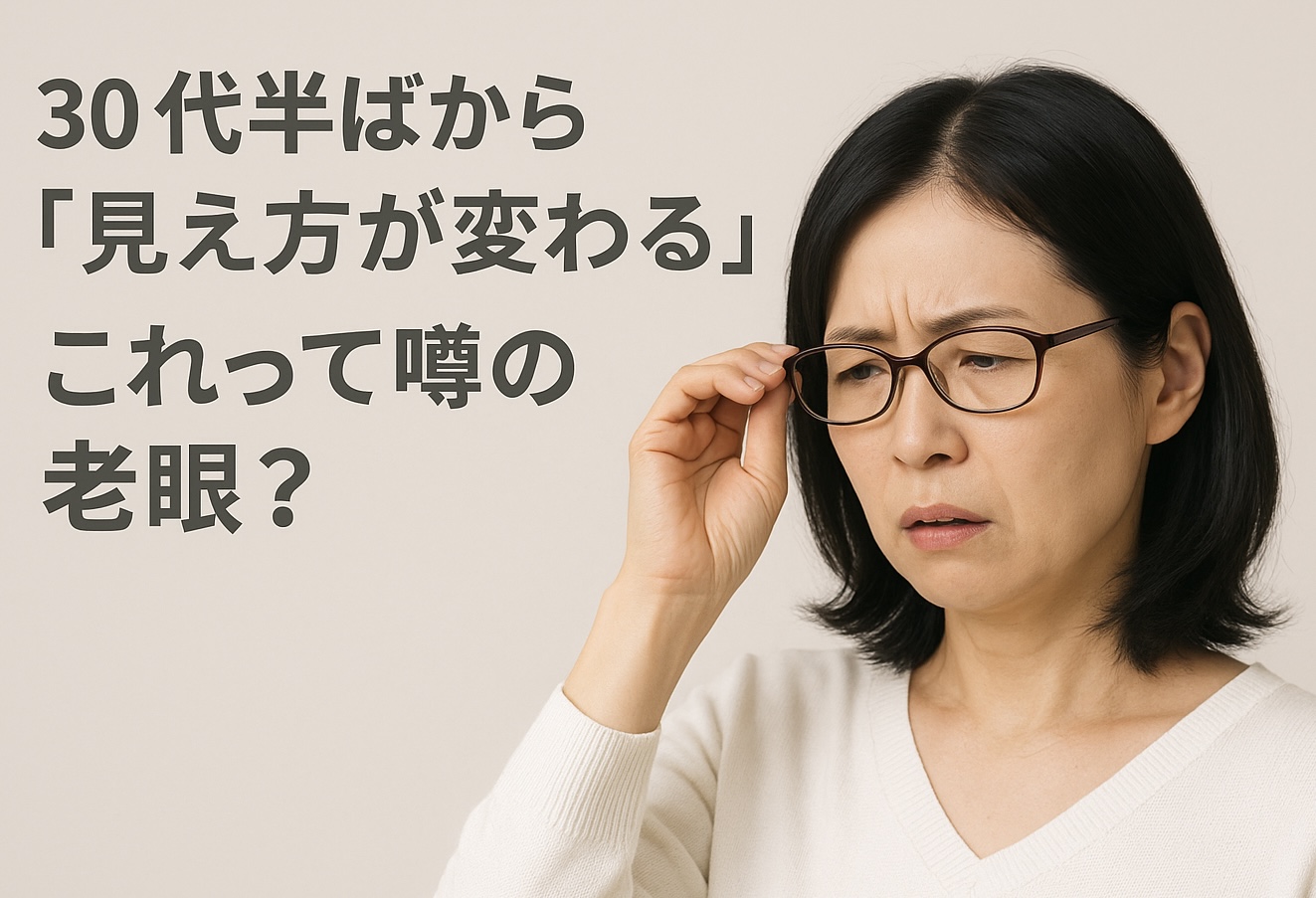2025年11月03

〜子どもの眼鏡の必要性を考える〜
春や秋に行われる「学校健診」で、「お子さんの視力が下がっています」と指摘を受けて来院されるご家族が毎年多くいらっしゃいます。
以前は小学校高学年〜中学生で多かった視力低下が、近年は低学年や幼児にも増えており、「子どもの近視」は社会的な問題になりつつあります。
ここでは、眼科医の立場から、学校健診で視力低下を指摘されたときの対応、そして眼鏡の必要性について詳しくお話しします。
子どもの視力が低下する主な原因
視力低下の原因の多くは「近視」です。近視とは、遠くのものがぼやけて見える状態で、眼球が前後に長くなり、光が網膜の手前でピントを結ぶことで生じます。
最近は、遺伝だけでなく、環境的な要因による近視の進行が増えています。代表的なものが次の3つです。
- スマートフォン・タブレットの長時間使用
近距離での画面操作は、目のピントを合わせる筋肉(毛様体筋)に強い負担をかけます。
勉強・動画視聴・ゲームなど、目を酷使する時間が長いほど「仮性近視(調節性近視)」が起こりやすくなります。 - 屋外活動の減少
近年の研究では、屋外で1日2時間以上過ごす子どもは近視の進行が遅いことがわかっています。
太陽光を浴びることで分泌される「ドーパミン」という物質が、眼球の伸びを抑える働きをするためです。 - 姿勢や照明環境の悪さ
暗い部屋での読書や、寝転がってのスマホ操作は、ピントの偏りを生み出します。
姿勢が悪いと左右の視力差や乱視を引き起こすこともあります。
学校健診の結果、「要受診」と言われたら
学校健診の視力検査はあくまで「スクリーニング(ふるい分け)」です。
検診で指摘された場合は、早めに眼科を受診しましょう。
健診では正確な屈折状態までは分からないため、「仮性近視」なのか「真の近視」なのかを区別する必要があります。
眼科では、以下のような検査を行い正確な度数と治療方針を決めます。
- 屈折検査(近視・遠視・乱視の測定)
- 調節機能検査(ピント合わせの能力)
- 必要に応じて調節麻痺薬(サイプレジンなど)を使用した精密検査
また、視力低下の原因が「斜視」「弱視」など別の病気にあるケースもあるため、必ず専門的な診察が大切です。
子どもに眼鏡をかけさせるべきか?
「まだ小さいのに、眼鏡をかけさせるのは早いのでは?」
多くの保護者が迷うポイントです。
結論から言えば、「見えにくい状態を放置すること」の方が問題です。
黒板が見えづらいと授業に集中できず、姿勢が前のめりになり、頭痛や肩こり、学習意欲の低下につながることがあります。
さらに、視力発達期(おおよそ8〜10歳頃)までにピントの合っていない状態を続けると、「弱視」と呼ばれる視力発達の障害が起こるリスクもあります。
眼鏡は「治療の一環」です。
適切な度数で視力を補正することで、目の発達を正常に保ち、近視の進行を遅らせる効果も期待できます。
大切なのは、「必要な時に、正しい眼鏡を使うこと」です。
最近では、
- 見る距離によって使い分ける「部分矯正眼鏡」
- 近視の進行を抑える「マイオピン点眼、リジュセア点眼」
- 「オルソケラトロジー(夜間装用コンタクト)」
など、治療の選択肢も増えています。お子さんの年齢や生活習慣に合わせて、最適な方法を眼科で相談しましょう。
ご家庭でできる近視予防・進行抑制の工夫
- 屋外で1日2時間以上過ごす
外遊びは近視予防の最も有効な方法の一つです。
日光を浴びながら遠くを見る時間を意識的に取りましょう。 - 30分ごとに目を休ませる
勉強やゲームの合間に1〜2分、遠くを見る「目の休憩」を取り入れましょう。 - 読書やスマホとの距離を30cm以上保つ
姿勢よく、顔を本や画面に近づけすぎないことが大切です。 - 寝る前1時間はスマホ・タブレットを控える
ブルーライトは目の疲れだけでなく、睡眠リズムにも悪影響を与えます。 - 十分な睡眠とバランスの良い食事
視力を守るためには全身の健康も欠かせません。ビタミンA、ルテイン、DHAなどを含む食品もおすすめです。
まとめ 〜見える力を未来につなぐために〜
学校健診で「視力低下」を指摘されたら、放置せず早めに眼科を受診しましょう。
近視は進行を完全に止めることは難しいものの、正しい環境づくりと適切な視力補正で進行を緩やかにすることが可能です。
眼鏡は「視力を守るためのパートナー」です。
見える世界が広がることで、子どもたちの学びや自信も大きく育ちます。
ご家庭でも日常の習慣を見直し、「見る力」を一緒に支えていきましょう。